|
|
芳野日記や東路日記にみる湯川屋
嘉永元年(1848年)氷室長翁の芳野日記によれば「みよしの山の湯川屋と云う宿にとまり、九日てんきよし宿を出で、まず蔵王権現へまうでさくら苗植えて・・・」とある。
さくらの植樹は単に観光のためではなく、蔵王権現への信仰に結びついたものであり、又当時の門前町の旅籠湯川屋の模様などがうかがわれる。
また、天保11年(1840年)小田宅子の東路日記などにも登場している。
|
|
|

役行者尊像(湯川屋所蔵) |
役行者尊像(湯川屋所蔵)
弘安九年(1286年)六月一八日、仏師慶俊によって作られた修験者の祖・役行者座像。
( 現在は奈良国立博物館に寄託 )
|
|
|
「役行者と修験道の世界」
毎日新聞社発行 1999年9月10日 |
|
|
6 木造役行者倚像 慶俊作
総高78.0センチ
鎌倉時代 弘安九年 ( 1286 )
吉野山上の個人宅に伝えられた像で、役行者像としては現存最古の在銘の基準作となる。檜材の寄木造り、彩色、彫眼の像で、頭体の根幹部を前後二材から作り、背面材は割首して内刳りを施す。胎内背面の墨書銘から、本像は弘安九年に阿闍梨「長命」が大願主となり、大仏師慶俊が制作したことが知られる。長頭巾を被り、内衣・法衣(大袖衣)に吊袈裟を前け、さらに蓑をマント状に懸けており、後世に流布する役行者像の基本的な服制を備えている。温厚な老相に表された佳品で、鎌倉期の行者像の様相を知る上で重要である。
(胎内腹部墨書銘)
持充□
金剛佛子阿闍梨長命
弘安九年戌丙六月十八日造立之大願主
大佛師慶俊伊与□
右志者為國主聖朝天長地久長者殿下佛法興隆父母師長
乃至有縁無縁一切衆生滅罪生善往生殊致舟誠所造立如
件
(胎内背面墨書銘)
□々未□□一之依斗功徳九品浄土往生ゝゝ
□□榮秀榮命等ヵ□□安□往法□
弘安九年戌丙六月十八日造立之大願主金剛佛子長命
南無八大金剛童子南無両部界曾諸尊
聖□
|
|
(胎内後頭部墨書銘)
大先達播广船越住侶
至徳三八月上 圓春房覚親辻□福
奉錐□拝之 同行圓實房義尊房
繪師□倉二附□
(マ丶)
大進阿闍梨十□房
一僧祗
| 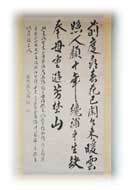 |
「頼山陽掛け軸」の内容
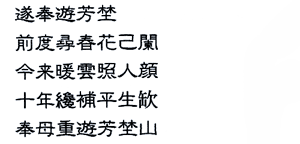
「掛け軸」の意味
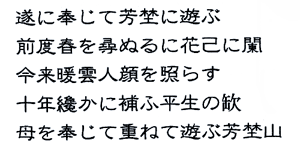 |
|
|